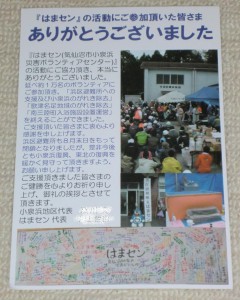ポートメッセ名古屋で10月4日、国土交通省中部地方整備局の音頭で「東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議」が開催された。9月29日付のプレスリリース(ウェブサイト掲載)によると、かなり仰々しい体制で臨むようだ。「船頭多くして船…」になりそうな気配も。
それにしても、長野県勢はよく対応してくれたよなぁ~というのが感想。愛知・岐阜・三重・静岡は当然としても、長野県はほとんど支援側となって、「持ち出し」が相当あるのではないか。もちろん、飯田下伊那地域の天竜川沿いは被害予想が出ており、まったく無縁というわけではないことは知っているが、それでも、全体の比率から考えても、やっぱり割に合わない。これを縁に、名古屋圏とつながりを強くして、何らかの経済効果を期待したいということだろうか。
個人的には、長野県が加わってくれるのは大変ありがたいと思っている。行政の思惑とは関係なく、市民レベルの交流や支援を続けてきたのに加え、公的な動きが加われば、さらに強固な関係を築けるからだ。
これまで、NPO法人飯田ボランティア協会や長野県社協とともに、長野県各地の災害ボランティアセンターの立ち上げ訓練に出かけ、関係作りに努めてきた。飯田市、高森町、軽井沢町、御代田町など。平成18年7月豪雨(長野県岡谷市の支援)もしてきた。平成20年8月末豪雨(愛知県岡崎市の支援)をしていただいた。飯田ボランティア協会の面々とは、東日本大震災の支援で、一緒に仙台市へも行った。いざというときに頼りになる存在だ。また、三遠南信災害ボランティアネットワークでは、浜松-豊川-飯田を核にして、災害ボランティアの交流活動も盛んだ。
新潟県堺の北信地域では豪雪対応も必要だ。飯山市社協が主催する「雪堀とうど塾」(除雪ボランティア講習と地域交流)にも2年ほど参加した。ここ数年参加できていないのが残念。この冬は、久しぶりに参加できたら…と考えている。飯山市社協さんには、企画をよろしくお願いしたい。
災害リスクは内容や規模が違っても、損得勘定抜きで相互支援できる(したいと思える)ような関係作りが、まず必要だ。交流が深まると、相手のよいところ、自分にはないもの、残して欲しいもの…、そういったかけがえのないものが見えてくる。そして、それを守りたくなってくる。
安曇野、伊那谷の豊かな自然、文化は、失いたくない。相互支援・交流を理由にして、長野へ出かけるのが楽しみになっている。リタイヤしたら、長野へ移住しようかなどと半分本気でで考えている。でも、「信濃の国」は未だになじめない(笑)。
2011 年 10 月 5 日( 水 )23 時 59 分 |
コメント(0)
カテゴリー:調査
タグ:,NPO法人飯田ボランティア協会, 三遠南信災害ボランティアネットワーク, 三重県, 仙台市, 信濃の国, 国土交通省中部地方整備局, 宮城県, 岐阜県, 岡崎市, 岡谷市, 平成18年7月豪雨, 平成20年8月末豪雨, 御代田町, 愛知県, 東日本大震災, 東海・東南海・南海地震対策中部圏戦略会議, 浜松市, 豊川市, 軽井沢町, 長野県, 長野県社会福祉協議会, 静岡県, 飯山市, 飯山市社会福祉協議会, 飯田市, 高森町
はまセン」とは、東日本大震災の復興支援のため、宮城県気仙沼市本吉町今朝磯に設置された「小泉浜災害ボランティアセンター」の愛称です。4月に立ち上がり8月末に閉鎖されたセンターで地域の多目的集会施設が避難所として使用されているところへ併設する形で運営されました。延べ1万人のボランティアが活動したそうです。
8月25日の記事「西尾市立西野町小学校で東日本大震災現地支援活動の報告」で紹介しているように、5月連休に私も活動に参加しました。
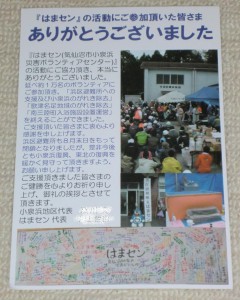
今日、写真のようなはがきの感謝状が届きました。はがきとはいえ1万人に送付するのは大変な作業だったと思います。最後の最後までお疲れ様です。はがきには地区代表とセンター長のお礼の挨拶とセンターが設置された多目的集会場で朝のミーティングをしている様子や、ボランティアの皆さんが書いた(私も書いた)寄せ書きの写真が印刷されています。
写真を見て、懐かしく思うとともに、もう一度お手伝いに…の思いが実現できなかったことが残念に思われます。JR線が復旧したら電車を乗り継いで、自分が活動をした気仙沼線蔵内駅に下り立ち、ボラセンまで歩きたいと思います。
何はともあれ、こうやって礼状を出す余裕が出てきたということは、着実に復興に向けて進んでいるということ。そう思うとうれしい限りです。これからも見守り続けたいと思います。
2011 年 10 月 3 日( 月 )23 時 59 分 |
コメント(0)
カテゴリー:災害救援
タグ:,宮城県, 東日本大震災, 気仙沼市, 気仙沼市小泉浜災害ボランティアセンター
名古屋大学大学院の川崎准教授の研究結果が掲載されました。まずは、この時期に誰もが考えたくないM9.0の想定でシミュレーションを実施して公開したことに敬意を表したいと思います。
中央防災会議の専門調査会でさえ、「対策できない想定、被害予想は無視」して「減災」などと言い訳をしている情けない状況で、批判を恐れず公開に踏み切るのは、勇気がいることだったろうと思います。
地元の自主防災会向けの啓発では、これまでは、素人判断なので…と前置きしながら、東日本大震災の津波被害と比べて、3連動地震の被害を漠然とイメージしていました。仙台市南部から名取市、岩沼市、亘理町にかけての広大な平地を内陸4~5kmまで津波が押し寄せたことを引き合いに出して、もし、同じような津波が来たとしたら海岸から内陸へ4~5kmの範囲はここらあたりまでだから、あなたの地域は水没…といった調子です。
まったく根拠のない条件設定ですが、イメージを持ってもらうためには、乱暴であったとしても過大評価をした被害想定をして、備えを促す必要があると思ってやっていました。早く専門家の予想が出て、それを基にした話をすれば、もっと説得力が増すのに…と、今か今かと待ちわびていました。
中日新聞に掲載された色分け地図によると、私が住んでいる西三河南部は、オレンジ色で、最大浸水深5~6mと絶望的な結果が出ています。「やっぱりねぇ」というのが第一印象で、はっきりと引導を渡された気がしました。
上記のような根拠のない素人の話よりも、説得力のある啓発ができると思い、ほっとしました。自分が住む地域の悲惨な予想を突きつけられて喜ぶのも変な話ですが、半年のモヤモヤが取れてすっきりしたのは事実です。
残念ながら、色分け地図はこまか過ぎて、また、道路や鉄道、官公署などが記載されていないので、自分の町内は…といったレベルの判断は困難です。大雑把な判断をするために、地図サイトの画像キャプチャを透過表示させて重ねてみました。
この予想結果では、西尾市南部は壊滅的で、矢作古川の両岸に広がる低地にある西尾市役所、警察署、消防署、保健所、名鉄西尾駅あたりの中心街は浸水深2~3mとなっており、行政機能は失われることが想像できます。
この結果を見て覚悟を決め、自主防災活動に火がつくことを期待したいと思います。というか火をつけて回ります。備えたものだけが救われる。この地に「津波てんでんこ」を真剣に普及させねば。
2011 年 10 月 2 日( 日 )23 時 59 分 |
コメント(1)
カテゴリー:調査
タグ:,亘理町, 仙台市, 名取市, 宮城県, 岩沼市, 想定東海・東南海・南海地震, 愛知県, 東日本大震災, 西尾市
次のページ »